普段の業務を行うときにこのようなお悩みを持ったことはありませんか?
社内のファイルサーバにアクセスしたいのに繋がらない。
WindowsUpdateでいつの間にかCPU使用率が高くなっていた。
ECサイトの稼働状況を毎日確認するのは大変だ。
これらのお悩みを予め予測する、解決するために行うのが死活監視です。今回は死活監視を行うべき理由やすぐ始めるための方法などをご紹介します。
死活監視とは?死活監視を行うべき理由とは?
死活監視とはサーバ機器やネットワーク機器、Webサイトなどシステムが正常に稼働しているかを確認するために行われます。他にもネットワークが正常に繋がっているか、システム上に怪しいログが記録されていないか、必要なアプリケーションが起動しているか等も確認する場合があります。
このような各システムの稼働状況を定期的に確認することで、システム停止に繋がるような状況を予め予測・防止し提供サービスの売り上げ機会損失を防止することができます。
死活監視を行う際には何を目的とした監視なのかを明確にする必要があります。
- 社内のファイルサーバが停止するのを防ぎたい・・・ファイルサーバのCPU使用率、メモリ使用量の監視
- 業務システムが停止していることを検知したい・・・アプリケーションの死活監視
- ECサイトが遅延しているかどうか確認したい・・・Webサーバの応答監視
サーバが起動しているかどうかを確認するだけであればPingコマンドで監視を行うことができます。ですがPingコマンドを定期的に実行するよう自動化する設定や、障害時の通知機能を構築する必要があるため、死活監視をすぐに始めることは難しいでしょう。
Pingコマンドの実行例などはこちらの記事で解説しています。
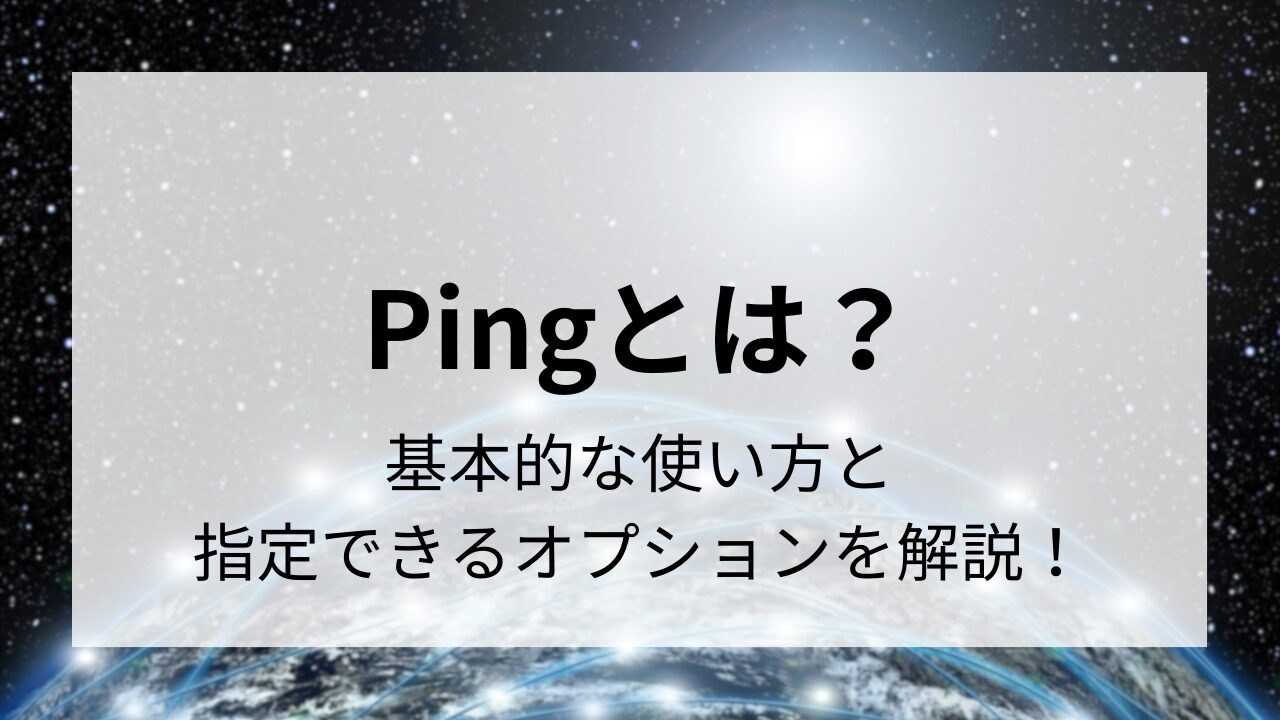
死活監視すぐに始めるには
監視を最も手軽に始めるには、死活監視専用のツールを使うことが挙げられます。専用のツールでは以下の業務を自動化することができます。
- 死活監視を決められた設定内容で定期的に実行する
- 障害を検知した際に指定した宛先へメール通知する
- 障害を検知した際のログを自動で保存する
死活監視ツールにはいくつか種類がありそれぞれで製品の特長が異なります。監視機能や通知機能の比較は重要ですが、使いやすさ・ランニングコスト・サポート対応の充実さなども検討する重要な要素です。
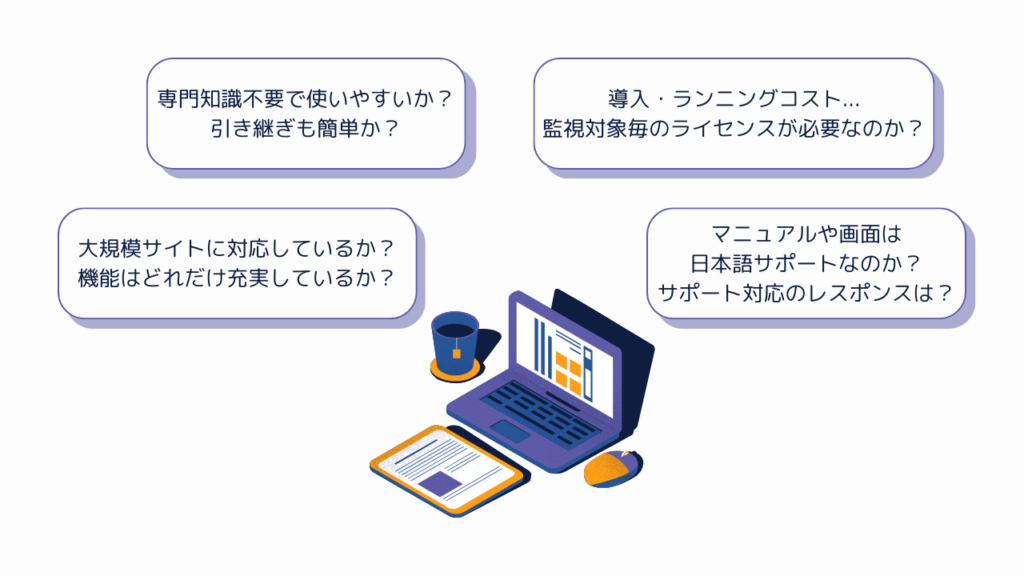
監視ツールのご紹介
サーバ・ネットワーク機器監視ツールであるNetKids iMarkでは上記のPingコマンドとSNMPコマンドの他にも、独自のプロトコルを用いた監視種別をご用意しており、以下をはじめとした様々な監視を行うことができます。
- データベースへの稼働状況
- Webサイトの応答時間
- Windows イベントログの出力内容
- 各アプリケーションの出力ログ
監視対象のサーバにエージェントを導入した場合は合計で100種類以上の監視種別をご利用いただけます。また多種多様な通知方法をご用意しております。通知方法はお客様に合わせたカスタマイズを行うことも可能です。
その他にも以下のような機能がございます。
- しきい値機能:「メモリ使用量が80%を超えていたらメール通知する」など、通知を行うためのしきい値を設定する
- スケジュール機能:指定した曜日、祝日では監視を停止する
- ブラウザ確認機能:既にご利用いただいているブラウザアプリケーションからiMarkの監視画面を簡素的に確認できる
- 通知テンプレート機能:複数の通知方法をまとめて実行する機能、通知のエスカレーションも可能
- マップ機能:任意の画像と監視項目を紐づけることで、視覚的にエラーの発生個所を表示する機能
- レポート機能:監視ログを分析して月次レポートや週次レポートを作成する機能
これらの機能は全て30日間の評価版にてお試しいただくことができます。評価時もサポートお問い合わせにも対応しておりますので、ぜひサーバ・ネットワーク監視にご活用ください。評価版はこちらからダウンロードいただけます。
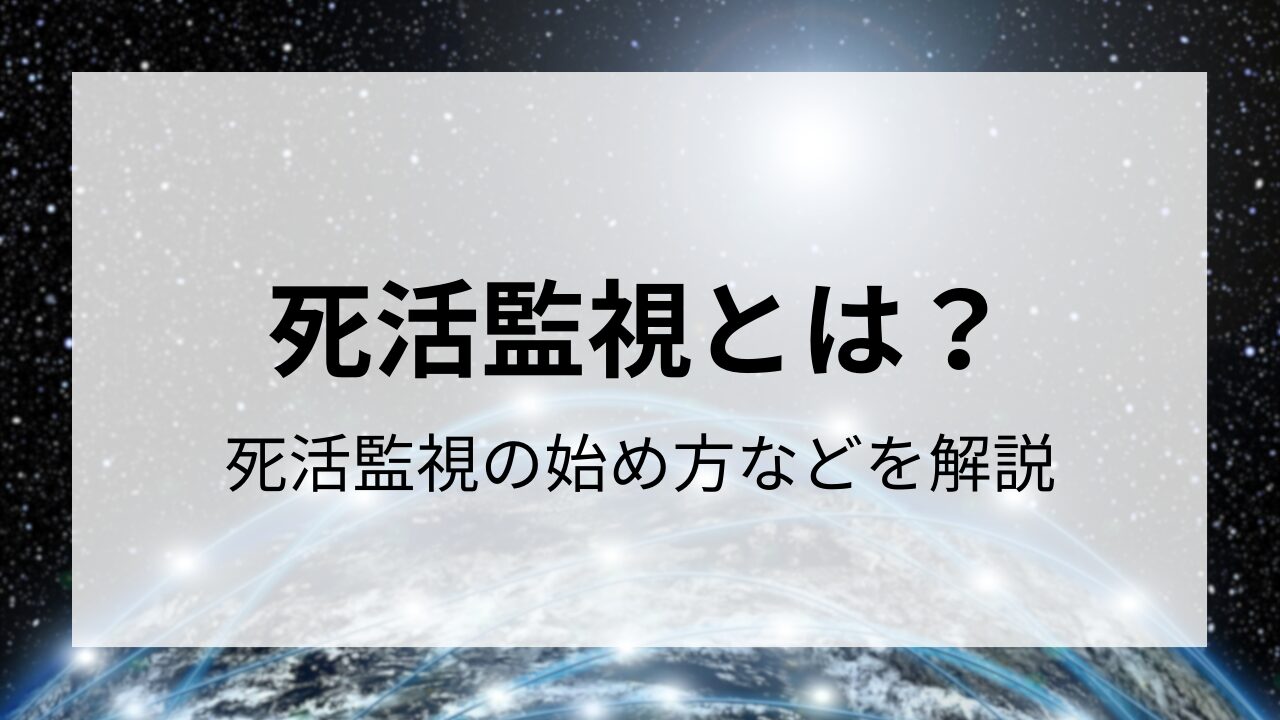
コメント